
僕って勉強がそこまでできるってわけではないですし、ひょっとしたらバカなのかもしれない…。

いつになく弱気ですね。
では、今回はバカとは何なのかについて考えていこうか。
目次
バカの正体
 自分は果たしてバカではないだろうか。
そんな疑問を生きている中で誰しも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
さて、バカの正体とは一体何でしょうか。
バカとは自分を過大評価している人のことを言うとされています。
つまり、自分が見えていない、自分を客観視できないのです。
あなたの周りに、どう見ても冴えないのに自分は「日本一」と豪語する人や「自分がモテないのはおかしい」などプライドだけが高い人はいませんでしたか。
バカは20くらいしかない自分の能力を80くらいあると本気で思い込んでいます。
逆に優秀な人は自分を小さく見せる傾向にあります。
「能ある鷹は爪隠す」ということわざにもあるように「自分なんてまだまだです」、「そんなことないですよ」と謙遜をするといった具合です。
自分は果たしてバカではないだろうか。
そんな疑問を生きている中で誰しも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
さて、バカの正体とは一体何でしょうか。
バカとは自分を過大評価している人のことを言うとされています。
つまり、自分が見えていない、自分を客観視できないのです。
あなたの周りに、どう見ても冴えないのに自分は「日本一」と豪語する人や「自分がモテないのはおかしい」などプライドだけが高い人はいませんでしたか。
バカは20くらいしかない自分の能力を80くらいあると本気で思い込んでいます。
逆に優秀な人は自分を小さく見せる傾向にあります。
「能ある鷹は爪隠す」ということわざにもあるように「自分なんてまだまだです」、「そんなことないですよ」と謙遜をするといった具合です。

自分を客観視できていない人をバカというのか。
僕は自分を正しく見れているだろうか。

そういう風に考えられているということはバカに該当しないように僕は考えるけど、どうだろうか⁉
バカが自分の実力を見誤る理由
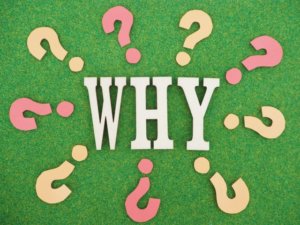 バカが自分の実力を見誤る理由は何でしょうか。
話は、原始時代にさかのぼります。
太古の昔、人間は150人~200人の群れを作り暮らしていました。
現代は、コンビニやインフラが発達しているため、一人で生きていくことは難しくありません。
しかし、その時代は群れからのけ者にされて一人になってしまうと死ぬ確率が高くなっていたのです。
今とは違い、一人になることは、死へと直結していたというわけです。
そして、私たちの心はこの頃に作られたものと考えられています。
だから、私たちは仲間外れにされることを怖く感じ、会社や学校で起こる些細な人間関係のトラブルにも大きな危機感を抱くのです。
バカは群れから追い出されないために自分を大きく見せていたというわけです。
では、どんな奴が仲間外れにされていたかというとバカ(空気が読めない)な奴とまとめることができます。
例えば、狩りをしていて獲物に忍び寄ったのに大声を出したり大きな足音を立てたのでは獲物に気取られ逃げられてしまいます。
つまり、一族全員の命が危ぶまれたのです。
バカな人は足手まといとレッテルを張られてしまい、群れから追い出されてしまいました。
そこで、バカな人は自分の能力が低いにもかかわらず、自分を大きく見せるようになりました。
バカが自分の実力を見誤る理由は何でしょうか。
話は、原始時代にさかのぼります。
太古の昔、人間は150人~200人の群れを作り暮らしていました。
現代は、コンビニやインフラが発達しているため、一人で生きていくことは難しくありません。
しかし、その時代は群れからのけ者にされて一人になってしまうと死ぬ確率が高くなっていたのです。
今とは違い、一人になることは、死へと直結していたというわけです。
そして、私たちの心はこの頃に作られたものと考えられています。
だから、私たちは仲間外れにされることを怖く感じ、会社や学校で起こる些細な人間関係のトラブルにも大きな危機感を抱くのです。
バカは群れから追い出されないために自分を大きく見せていたというわけです。
では、どんな奴が仲間外れにされていたかというとバカ(空気が読めない)な奴とまとめることができます。
例えば、狩りをしていて獲物に忍び寄ったのに大声を出したり大きな足音を立てたのでは獲物に気取られ逃げられてしまいます。
つまり、一族全員の命が危ぶまれたのです。
バカな人は足手まといとレッテルを張られてしまい、群れから追い出されてしまいました。
そこで、バカな人は自分の能力が低いにもかかわらず、自分を大きく見せるようになりました。

原始時代からの修正ってなかなか壮大な話ですね。

所詮、人間も動物ですからね。変わらない部分もあるということですね。
優秀な人が謙虚な理由
 前項でも述べましたが、太古の昔、人間は150人~200人の群れを作り暮らしていました。
そこで、生き延びて子孫を残すためには、ほかの男性や女性よりも異性に選ばれて自分の有能さをアピールする必要がありました。
今でいうと、高身長、高学歴、高収入といった具合です。
しかし、むやみやたらに自分の優秀さをアピールすれば良かったかというとそういうわけでもありませんでした。
一見アピールした方が、良いように思われます。
しかし、目立ちすぎると同性から反感を買ったりして引きずりおろされたり、恨まれたりする可能性も多くありました。
優秀な同僚は、時に恋のライバルになるというような印象です。
実際に、私たちの脳は自分より優れた人を見ると損失を感じることが分かっています。
逆に、自分より劣った人を見ると報酬を感じるようにできています。
例えば、ワイドショーなんかで優秀な人がたたかれている場面がよくありますが、それを食い入るように見てしまうのはこの感覚が影響しているのです。
ニュースやSNSなどでひっきりなしに経営者や政治家、芸能人、有名人という人がたたかれているのは私たちの心理を突いているからなのです。
つまり、今も昔も優秀なことがあからさまになっていると四方八方から足を引っ張られてしまうというわけです。
だから、優秀な人はあえて自分を小さく見せてしたたかにふるまうのです。
前項でも述べましたが、太古の昔、人間は150人~200人の群れを作り暮らしていました。
そこで、生き延びて子孫を残すためには、ほかの男性や女性よりも異性に選ばれて自分の有能さをアピールする必要がありました。
今でいうと、高身長、高学歴、高収入といった具合です。
しかし、むやみやたらに自分の優秀さをアピールすれば良かったかというとそういうわけでもありませんでした。
一見アピールした方が、良いように思われます。
しかし、目立ちすぎると同性から反感を買ったりして引きずりおろされたり、恨まれたりする可能性も多くありました。
優秀な同僚は、時に恋のライバルになるというような印象です。
実際に、私たちの脳は自分より優れた人を見ると損失を感じることが分かっています。
逆に、自分より劣った人を見ると報酬を感じるようにできています。
例えば、ワイドショーなんかで優秀な人がたたかれている場面がよくありますが、それを食い入るように見てしまうのはこの感覚が影響しているのです。
ニュースやSNSなどでひっきりなしに経営者や政治家、芸能人、有名人という人がたたかれているのは私たちの心理を突いているからなのです。
つまり、今も昔も優秀なことがあからさまになっていると四方八方から足を引っ張られてしまうというわけです。
だから、優秀な人はあえて自分を小さく見せてしたたかにふるまうのです。

たしかに、僕の周りにいつ天才や秀才は自分のことを大きく見せないような気がします。

逆に、私は…っていう人を見たら、一歩ひいてしまうよね。
バカの問題点
 心理学者のダニング博士とクルーガー博士は「能力の低いものは、自分の能力が低いことを正しく認識できているのか」を確かめるために実験を行いました。
本実験では、頭の悪い生徒と頭の良い生徒の二組に分け、数学的な能力や国語の能力、そしてユーモアのセンスなどを図るテストを受けてもらい、その結果と自己評価を比較するという内容でした。
その結果、頭の悪い学生は、実際の成績が12点だったにもかかわらず、自分たちの点数は68点だと思い込んでいたということが分かりました。
つまり、頭の悪い生徒は自分を5倍以上も過大評価していたことになります。
一方、頭のいい生徒は実際の点数が86点もあったにもかかわらず自分たちの能力は74点しかないと評価していたそうです。
本実験から、バカは自分を過大評価し優秀な人は自分を過小評価するということが分かります。
また、バカな人は自分を過大評価していることに全く気付いていません。
そのため、勉強ができない人ほど自分のことを勉強ができると思い込んでいるし、ユーモアのない人ほど自分をお笑い芸人並みに面白いと勘違いしていたりするわけです。
結果を見せつければ改善の余地あると期待するのですが、彼らに客観的な事実を説明したとしてもその事実は正しく理解されません。
心理学者のダニング博士とクルーガー博士は「能力の低いものは、自分の能力が低いことを正しく認識できているのか」を確かめるために実験を行いました。
本実験では、頭の悪い生徒と頭の良い生徒の二組に分け、数学的な能力や国語の能力、そしてユーモアのセンスなどを図るテストを受けてもらい、その結果と自己評価を比較するという内容でした。
その結果、頭の悪い学生は、実際の成績が12点だったにもかかわらず、自分たちの点数は68点だと思い込んでいたということが分かりました。
つまり、頭の悪い生徒は自分を5倍以上も過大評価していたことになります。
一方、頭のいい生徒は実際の点数が86点もあったにもかかわらず自分たちの能力は74点しかないと評価していたそうです。
本実験から、バカは自分を過大評価し優秀な人は自分を過小評価するということが分かります。
また、バカな人は自分を過大評価していることに全く気付いていません。
そのため、勉強ができない人ほど自分のことを勉強ができると思い込んでいるし、ユーモアのない人ほど自分をお笑い芸人並みに面白いと勘違いしていたりするわけです。
結果を見せつければ改善の余地あると期待するのですが、彼らに客観的な事実を説明したとしてもその事実は正しく理解されません。
例えば以下のような言い訳をしてはぐらかすでしょう。 ・うっかりミスが多いだけ ・その時は調子が優れなかった
だから、自分の評価を修正しないばかりかますます自分の能力に自信を持つという悪循環にはまっていきます。 なぜなら、バカの頭の中では自分は天才で回りがバカに見えているからです。 そのため、自分より下だと思っている奴に何かを言われても全く聞き耳を持たないし、理解もできません。
バカに現実を突きつけても理解できないなんてなかなかに辛辣な意見ですね。

謙虚さと頭の良さにも大きな相関関係がありそうですね。
日本の抱えるバカへの問題
 実は、日本人の三人に一人が日本語が正しく読めないと言います。
実際に、日本を含む38か国(イギリスやアメリカ)で言語力や読解力、数学的な能力、ITスキルといったあらゆる能力が測られました。
その結果、「日本人の3分の1は日本語を読めないこと」や「日本人の3分の1以上が小学校3~4年生以下の数学能力しかないこと」、「パソコンを使った基本的な仕事ができる日本人は1割以下」という最悪な結果が判明しました。
ここでいう「日本語が読めない」というのは日本語を正しく理解できないということです。
つまり、文字を追うことはできても、その文字が何を意味しているのかを理解できないということです。
ホリエモンは、「字を読めない人の方が圧倒的に多い。話し言葉だと分かるみたいです」と言っています。
つまり、説明書を読んでも理解できるのは3割程度の人のみということになります。
実際、私も仕事でチャットを使うことがありましたが意味不明な文章を打っている人がいたような気がします(私の読解力不足だったら恥ずかしいですが…)。
現在、誰もが当たり前のように使うようになったlineのスタンプですが、普及した背景には我々の言語力の低下があるのかもしれません。
さらに、世界中と比べると日本はまだ頭がいい部類に入っているというのも驚きです。
実は、日本人の三人に一人が日本語が正しく読めないと言います。
実際に、日本を含む38か国(イギリスやアメリカ)で言語力や読解力、数学的な能力、ITスキルといったあらゆる能力が測られました。
その結果、「日本人の3分の1は日本語を読めないこと」や「日本人の3分の1以上が小学校3~4年生以下の数学能力しかないこと」、「パソコンを使った基本的な仕事ができる日本人は1割以下」という最悪な結果が判明しました。
ここでいう「日本語が読めない」というのは日本語を正しく理解できないということです。
つまり、文字を追うことはできても、その文字が何を意味しているのかを理解できないということです。
ホリエモンは、「字を読めない人の方が圧倒的に多い。話し言葉だと分かるみたいです」と言っています。
つまり、説明書を読んでも理解できるのは3割程度の人のみということになります。
実際、私も仕事でチャットを使うことがありましたが意味不明な文章を打っている人がいたような気がします(私の読解力不足だったら恥ずかしいですが…)。
現在、誰もが当たり前のように使うようになったlineのスタンプですが、普及した背景には我々の言語力の低下があるのかもしれません。
さらに、世界中と比べると日本はまだ頭がいい部類に入っているというのも驚きです。

ホリエモンの言葉に今の日本の言語問題のすべてが集約されている気がします。

日本語を正しく使うためにも読書の習慣は身につけておく必要がありますね。
バカと話し合いをすると損をする
 実際に頭のいい人とバカが一緒に議論すると、バカに引きずられて合理的な判断ができなくなることが分かっています。
認知心理学者のバハトル・バーミラが行った実験では、優秀な人と優秀な人が話し合いをするとプラスの結果が得られるのに対し、どちらか一方が劣る場合は話し合いがどんどん悪くなり、最終的にはコイントスで意思決定した方がましになることを突き止めました。
つまり、バカと話し合うくらいなら、一人で意思決定した方がましというわけです。
「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがありますが、それはそこそこ優秀な人が三人集まった場合に限るのです。
動画配信を行っている「ネットフリックス」は優秀な人だけを残して、それ以外の社員を解雇したところ生産性が大きく向上しました。
さて、日本の政治に話を移してみます。
日本では幾度となく政治の方策が変わってきましたが、あまりうまくいっていないような気がします。
さて、それはなぜでしょうか。
一説に、民主主義が上手くいかないのはバカと優秀な人が一緒に決めるからというものがあります。
会社であれば優秀な人だけを採用することができるかもしれませんが、民主主義ではみんなで何かを決めなければなりません。
選挙などでは、政治家が「消費税を上げるな」や「NHKをぶっ壊す」などと聞こえの良い言葉を声高に言っています。
そして、甘い言葉に誘われてバカは考えなしに政治家に票を投じてしまうわけです。
このようにバカと優秀な人が一緒になって決めるため民主主義はなかなかうまく機能しない側面があります。
それなら、頭のいい人だけで決める独裁国家であるシンガポールや中国の方が経済発展という面で考えればよいのかもしれません。
実際に頭のいい人とバカが一緒に議論すると、バカに引きずられて合理的な判断ができなくなることが分かっています。
認知心理学者のバハトル・バーミラが行った実験では、優秀な人と優秀な人が話し合いをするとプラスの結果が得られるのに対し、どちらか一方が劣る場合は話し合いがどんどん悪くなり、最終的にはコイントスで意思決定した方がましになることを突き止めました。
つまり、バカと話し合うくらいなら、一人で意思決定した方がましというわけです。
「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがありますが、それはそこそこ優秀な人が三人集まった場合に限るのです。
動画配信を行っている「ネットフリックス」は優秀な人だけを残して、それ以外の社員を解雇したところ生産性が大きく向上しました。
さて、日本の政治に話を移してみます。
日本では幾度となく政治の方策が変わってきましたが、あまりうまくいっていないような気がします。
さて、それはなぜでしょうか。
一説に、民主主義が上手くいかないのはバカと優秀な人が一緒に決めるからというものがあります。
会社であれば優秀な人だけを採用することができるかもしれませんが、民主主義ではみんなで何かを決めなければなりません。
選挙などでは、政治家が「消費税を上げるな」や「NHKをぶっ壊す」などと聞こえの良い言葉を声高に言っています。
そして、甘い言葉に誘われてバカは考えなしに政治家に票を投じてしまうわけです。
このようにバカと優秀な人が一緒になって決めるため民主主義はなかなかうまく機能しない側面があります。
それなら、頭のいい人だけで決める独裁国家であるシンガポールや中国の方が経済発展という面で考えればよいのかもしれません。

「ネットフリックス」の事例と民主主義の考察すごくおもしろかったです。

様々な事例を探して考える癖を養うことも日本語を扱う上では必要な能力かもしれませんね。
無知なことは悪いことではない
 バカと無知は違います。
辞書を引くと、バカとは「愚かなこと」とされています。
自分が物事を認識していないことすら分かっていないという具合です。
一方、無知とは「知識のないこと」とされています。
つまり、自分が分かっていないことを認識している状態です。
この意味の違いは大きいです。
自分が分からないことを自覚できれば調べる努力ができるし、人に聞くこともできるでしょう。
無知なことは悪いことではありません。
分からないのなら学べば良いのです。
そもそもすべてを知り尽くしている人間なんて存在しません。
だから、自分が無知なのであれば勉強して知識を補填すればよいのです。
その繰り返しで人生は豊かになっていくでしょう。
また、バカは学べない人とも言い換えることができるでしょう。
バカは自分が分からないということを認識していません。
また、他人からフィードバックを受け取ってもどうしていいのかわからず終わります。
分からないことが分からないから何も恥ずかしくないのです。
また、自分を過大評価しているから人の助言を素直に聞きいれることができません。
私たちもバカにという状態に陥ってしまわぬように、自分を過大評価せず、もし分からないことがあれば素直に「わからない」と学び続ける姿勢を大事にしていきましょう。
バカと無知は違います。
辞書を引くと、バカとは「愚かなこと」とされています。
自分が物事を認識していないことすら分かっていないという具合です。
一方、無知とは「知識のないこと」とされています。
つまり、自分が分かっていないことを認識している状態です。
この意味の違いは大きいです。
自分が分からないことを自覚できれば調べる努力ができるし、人に聞くこともできるでしょう。
無知なことは悪いことではありません。
分からないのなら学べば良いのです。
そもそもすべてを知り尽くしている人間なんて存在しません。
だから、自分が無知なのであれば勉強して知識を補填すればよいのです。
その繰り返しで人生は豊かになっていくでしょう。
また、バカは学べない人とも言い換えることができるでしょう。
バカは自分が分からないということを認識していません。
また、他人からフィードバックを受け取ってもどうしていいのかわからず終わります。
分からないことが分からないから何も恥ずかしくないのです。
また、自分を過大評価しているから人の助言を素直に聞きいれることができません。
私たちもバカにという状態に陥ってしまわぬように、自分を過大評価せず、もし分からないことがあれば素直に「わからない」と学び続ける姿勢を大事にしていきましょう。

「バカとは状態である」か。つまりどんな人もバカになり得るということが言えそうですね。

絶えず自己研鑽して自分をアップデートしていかないといけませんね。


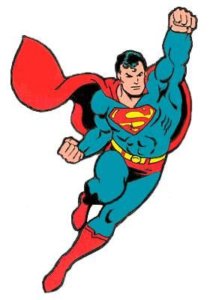



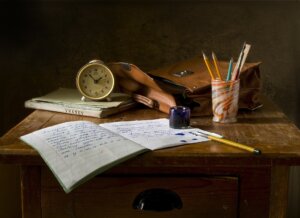

コメント